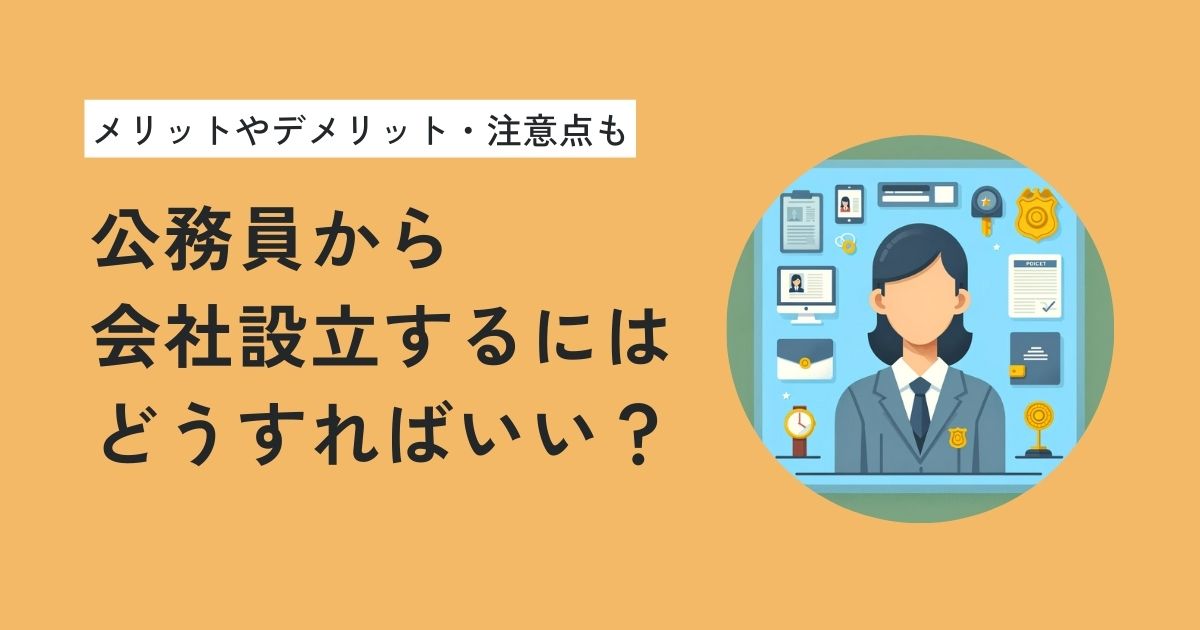公務員として働きながら、会社設立の夢を抱いている方は少なくないでしょう。しかし、公務員が会社設立をするには、法律や職務上の制約があり、簡単には実現できません。本記事では、公務員が会社設立をする際の注意点やポイントを解説します。
関連記事:起業するには何をしたらいい?方法や流れ、手続きなど事前準備を解説
公務員の起業・会社設立が難しい理由
公務員が副業としての起業や会社設立を考えた場合、複数の障壁に直面します。ここでは、起業が難しいとされる3つの主な理由を紹介します。
- 法律による制限がある
- 職務専念義務の観点から
- 利益相反を避けるため
これらの要因について詳しく見ていきます。
1. 法律による制限がある
公務員が会社設立をすることは、法律によって禁止されています。具体的には、国家公務員法第104条や地方公務員法第99条に規定されています。これらの法律では、公務員は「職務以外の営利を目的とする事業に従事し、又はその事業に関与してはならない」と定められています。つまり、公務員が自分で会社を設立したり、他人の会社に役員や株主として参加したりすることは法律違反となるのです。
2. 職務専念義務の観点から
公務員が会社設立をすることは、職務専念義務に反するとも言えます。職務専念義務とは、公務員が自分の職務に専念し、他の事業や活動に時間や労力を割かないことを求められる義務です。公務員が会社設立をする場合、その経営や運営に関わることになりますが、これは職務以外の事業に従事することに当たります。したがって、職務専念義務に違反する可能性があります。
3. 利益相反を避けるため
公務員が会社設立をすることは、利益相反を招く恐れがあります。利益相反とは、公務員が自分の職責と私的な利益との間で葛藤や衝突が生じる状況のことです。例えば、公務員が自分の会社の業種や商品と関係のある部署や業務に携わっている場合、自分の会社に有利な判断や処理を行う可能性があります。これは、公正・中立・透明な行政を損なうことになります。
公務員が会社設立をする方法
公務員が会社設立をするには、法律や職務上の制約に注意しなければなりません。以下では、公務員が会社設立をする方法について解説します。
関連記事:会社設立の流れ5ステップ|必要な手続きや費用・メリットを詳しく解説
所属先の許可を得る
公務員が会社設立をする場合、まず所属先の許可を得る必要があります。公務員法では、公務員は他の職業に従事することができないと定められています。しかし、所属先の長の許可があれば、例外的に他の職業に従事することができます。この場合、会社設立も他の職業に該当します。
所属先の長の許可を得るためには、会社設立の目的や内容、役割や時間などを詳細に申請書に記入し、提出する必要があります。所属先の長は、申請書を審査し、公務員の職務専念義務や利益相反などに問題がないか判断します。許可が下りれば、公務員は会社設立を進めることができます。
非営利企業として報酬を受け取らない
公務員が会社設立をする場合、非営利企業として運営する方法があります。つまり、会社から報酬や配当などの利益を受け取ることはできません。公務員法では、公務員は他から報酬や利益を受け取ることができないと定められています。これは、公務員が自分の利益のために職務を不正に行うことを防ぐためです。
非営利企業として運営する場合、会社の収益はすべて事業費や寄付などに充てる必要があります。また、会計や税金などの管理も厳格に行う必要があります。非営利企業として登録することで、税制上の優遇措置を受けることもできます。
家族を役員にする
公務員が会社設立をする場合、自分以外の家族や友人などを役員にすることも一つの方法です。この場合、自分は役員ではなく単なる顧問や相談役として関わることになります。これは、公務員法では、公務員は他人の事業に関与することも禁止されているからです。
家族や友人などを役員にする場合、自分が実質的に経営権を握っているような状況は避ける必要があります。また、家族や友人なども公務員法に違反しないように注意しなければなりません。例えば、公務員の職務に関係する事業を行ったり、公務員に便宜を求めたりすることはできません。
公務員の会社設立が認められるケース
公務員が会社設立をするには、一般的には所属先の許可が必要です。しかし、許可を得られるケースは限られており、以下のような条件が満たされている場合にのみ可能です。
社会貢献活動として想定される場合
公務員が会社設立をする目的が、社会貢献活動として想定される場合は、許可が下りる可能性があります。例えば、環境保護や福祉などの分野で、公益性の高い事業を行う場合です。この場合、会社設立の動機が自己利益ではなく、社会的な価値創造であることを明確にする必要があります。
公共サービスの拡張を目的としている場合
公務員が会社設立をする目的が、公共サービスの拡張を目的としている場合も、許可が下りる可能性があります。例えば、地方自治体や国家機関などの業務を補完・支援するような事業を行う場合です。この場合、会社設立の動機が公共の利益に資することを明確にする必要があります。
公務員が会社設立をするメリット
ここでは、公務員が会社設立をするメリットについて3つ紹介します。
公務経験を活かした事業展開ができる
公務員は、国や地方自治体の様々な業務に携わっています。その中で、法律や制度、行政手続きなどの専門知識やノウハウを身につけているでしょう。また、公務員は多くの人と関わり、コミュニケーション能力や交渉力も高めているはずです。これらのスキルや知識は、会社設立にも役立ちます。例えば、公務員が会社設立をする場合、以下のような事業展開が考えられます。
- 公共サービスの提供
- 法律や制度の支援
- 行政手続きの代行
安定した退職後のキャリアパスを確立できる
公務員は、一般的に定年制度があります。定年後は再雇用制度や再就職支援制度などがありますが、それでも収入や働き方に変化が生じることが多いでしょう。また、定年後も自分の能力や経験を活かして働きたいという希望もあるかもしれません。
そんなとき、自分で会社を設立していれば、安定した退職後のキャリアパスを確立できます。自分で会社を経営すれば、自分のペースで働くことができますし、自分の興味や目標に沿って事業を展開することもできます。また、自分で会社を設立すれば、自分だけでなく他の人にも雇用機会を提供することができます。これは、社会的な意義も大きいと言えます。
社会貢献と個人の利益を同時に追求できる
公務員は、国や地方自治体のために働いています。そのため、公務員は社会貢献の意識が高いと言えます。しかし、公務員は、自分の利益や自由度に制約があります。例えば、公務員は、職務専念義務や利益相反の観点から、副業や兼業を禁止されている場合が多いです。また、公務員は、給与や昇進などの評価制度によって、自分の能力や成果が十分に反映されないと感じることもあるかもしれません。
そんなとき、自分で会社を設立すれば、社会貢献と個人の利益を同時に追求できます。自分で会社を設立すれば、自分のスキルや知識を活かして社会に貢献することができますし、自分の努力や成果に応じて収入や評価を得ることもできます。また、自分で会社を設立すれば、自分の好きなことややりたいことを実現することもできます。これは、個人的な満足感も高いと言えます。
公務員が会社設立をするデメリット
公務員が会社設立をするメリットは多くありますが、デメリットも無視できません。ここでは、公務員が会社設立をする際に注意すべきデメリットについて解説します。
利益相反が生じる可能性がある
公務員が会社設立をする場合、自分の職務と自分の会社の利益が衝突する可能性があります。例えば、自分の会社が受注したい公共事業の入札に関わる職務を担当している場合、不正な情報提供や不公平な評価を行う恐れがあります。また、自分の会社と競合する他の企業に対して、不利な処分や規制を行う可能性もあります。このような利益相反は、公務員の信用や公共の利益を損なうだけでなく、刑事罰や損害賠償の対象となる場合もあります。
公務員法による規制に違反するリスクがある
公務員は、公務員法やその他の法令によって、会社設立に関する様々な規制を受けています。例えば、公務員法第99条では、公務員は「職務以外に営利を目的とする事業に従事し、又はその事業に関与してはならない」と定められています。この規定に違反した場合、停職や減給などの懲戒処分や免職処分を受ける可能性があります。
また、公務員法第100条では、退職後も一定期間内には「自己又は第三者のために営利を目的とする事業に従事し、又はその事業に関与してはならない」と定められています。この規定に違反した場合、退職手当の返還や刑事罰を受ける可能性があります。
会社設立にコストがかかる
公務員が会社設立をする場合、会社の種類や規模によって異なりますが、一般的には以下のようなコストがかかります。
- 登記費用:株式会社の場合は約5万円、有限会社の場合は約2万円
- 印紙代:株式会社の場合は資本金の0.7%(最低15万円)、有限会社の場合は資本金の0.4%(最低6万円)
- 設立時税金:株式会社の場合は資本金の1%(最低10万円)、有限会社の場合は資本金の0.5%(最低5万円)
- 顧問弁護士や税理士などの報酬:株式会社の場合は約30万円~50万円、有限会社の場合は約20万円~30万円
これらのコストは、公務員として働きながら負担するのは困難な場合が多いでしょう。また、会社設立後も、会計や税務などの管理にもコストがかかります。
関連記事:会社設立の流れ5ステップ|必要な手続きや費用・メリットを詳しく解説
公務員の会社設立はリスクもある
公務員が会社設立をするには、法律や職務専念義務、利益相反などの問題に注意しなければなりません。しかし、公務員の会社設立は不可能ではありません。所属先の許可を得たり、非営利企業として活動したり、家族を役員にしたりする方法があります。
公務員が会社設立をする場合は、慎重に準備を進めることが重要です。