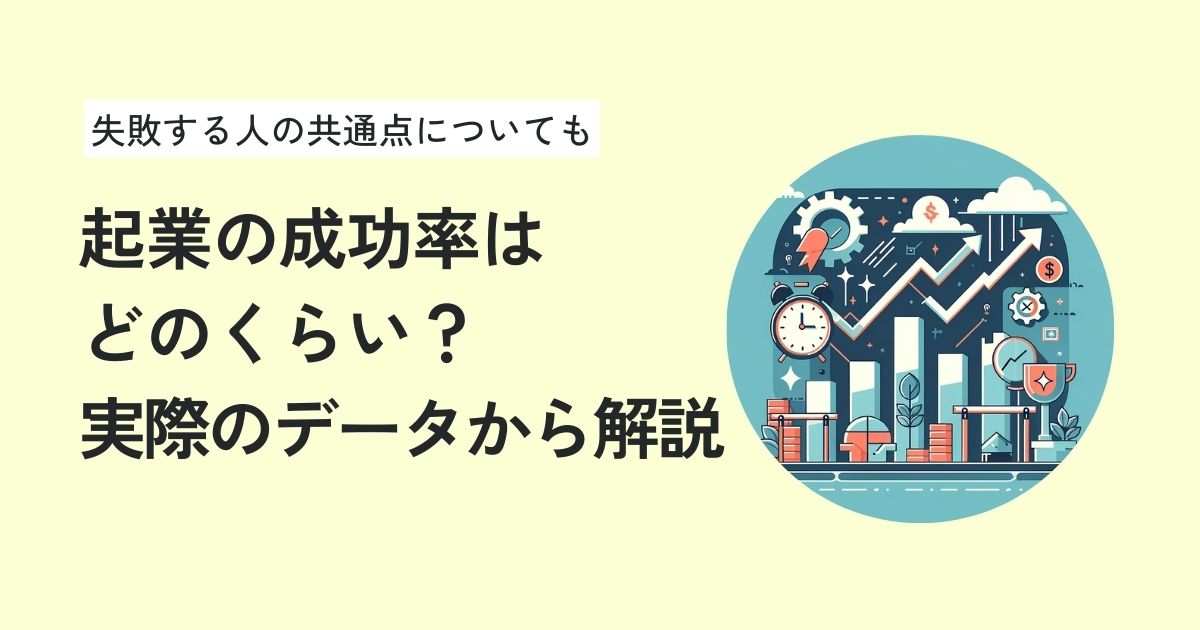起業というと、自分の夢を実現したり、社会に貢献したりする素晴らしいことのように思えますが、実際には多くの困難やリスクがあります。起業に挑戦した人の中で、どれくらいの割合が成功しているのでしょうか?また、成功するためにはどのような要素が重要なのでしょうか?
この記事では、日本における起業の成功率や失敗率をデータから読み取り、成功事例を紹介しながら、起業を考えている方に役立つ情報をお伝えします。
関連記事:起業するには何をしたらいい?方法や流れ、手続きなど事前準備を解説
日本における実際の起業成功率
ここでは、日本における企業の生存率を見てみましょう。
日経ビジネスによるベンチャー企業の生存率
日経ビジネス『「創業20年後の生存率0.3%」を乗り越えるには』には、ベンチャー企業の生存率は創業から5年後は15.0%、10年後は6.3%。20年後は0.3%と明記されています。
起業後20年の生存率は非常に低く、日本のベンチャー企業は長期的な存続が困難であるとされています。これらの統計から、日本のベンチャー企業の生存率は比較的低いと言えます。
中小企業庁のデータによる中小企業の生存率
平成29年度に発表された中小企業白書「起業の実態の国際比較」によると、日本における中小企業の生存率は以下のようになっています。
- 起業後1年: 95.3%
- 2年: 91.5%
- 3年: 88.1%
- 4年: 84.8%
- 5年: 81.7%
データによると、日本はベンチャー企業の生存率は低いものの、中小企業の生存率は海外と比較しても高いことがわかります。
起業失敗の主な要因
ここでは、起業失敗の主な要因として、販売不振、既往のしわ寄せ、過小資本の3つを取り上げます。
その他の要因については下記でも解説しています。
関連記事:起業がほとんど失敗すると言われる理由|成功のためのポイントも解説
販売不振
起業家が最も恐れるのは、自分の商品やサービスに需要がないことです。市場調査や競合分析を十分に行わずに、自分の思い込みや好みだけで開発したものは、顧客のニーズに合わない可能性が高いです。また、マーケティングや広告に力を入れずに、口コミだけで売れると考えるのも危険です。
販売不振に陥ると、収入が減り、経費や借金の返済に困るようになります。その結果、資金繰りが悪化し、廃業に追い込まれるケースが多く見られます。
既往のしわ寄せ
既往のしわ寄せとは、経営状態が悪化しているにもかかわらず、具体的な対策を講じないまま過去の資産を消耗し、倒産に至ることを指します。例えば、過去の成功体験や資産に頼りながら現在の経営課題に対処せずに経営を続けることで、企業の存続が危ぶまれることなどが挙げられます。
既往のしわ寄せを放置すると、新たな事業の発展を妨げるだけでなく、法的な問題や訴訟に巻き込まれるリスクも高まります。
過小資本
起業失敗の主な要因のひとつに、過小資本が挙げられます。過小資本とは、事業を開始する際に必要な資金が不足している状態のことです。過小資本に陥ると、事業の拡大や改善に必要な投資ができなくなり、競争力が低下したり、収益性が悪化したりするリスクが高まります。
過小資本の原因はさまざまですが、以下のようなものが考えられます。
- 事業計画の作成や見直しが不十分で、必要な資金を見積もれなかった
- 自己資金や借入金が少なく、外部からの資金調達が難しかった
- 売上や利益の見込みが甘く、キャッシュフローが悪化した
- 固定費や変動費が想定以上にかかり、利益率が低下した
過小資本を回避するためには、事業計画の作成や見直しを定期的に行い、必要な資金を正確に把握することが重要です。また、自己資金や借入金だけでなく、クラウドファンディングやベンチャーキャピタルなどの外部からの資金調達の可能性も検討することも有効です。
起業に失敗する人の特徴
起業に失敗する人にはいくつかの共通の特徴があり、以下の3つのポイントが特に重要です。
計画性が欠如している
起業には、ビジネスプランやマーケティング戦略など、様々な計画が必要です。しかし、計画性が欠如している人は、目標や期限を設定せずに行動します。その結果、効率が悪くなり、競合他社に遅れをとったり、資金が枯渇したりする可能性が高くなります。計画性が欠如している人は、自分の弱点を認めて、専門家やメンターに助言を求めることが重要です。
柔軟性が不足している
変化する市場の需要や技術の進化に速やかに適応できる柔軟性は、起業家にとって重要な資質です。失敗する起業家の中には、固定した考え方ややり方にこだわりすぎ、新しいチャンスを見逃したり、必要な変更を受け入れられない場合があります。このような人は、状況を正確に評価し、必要に応じて方向性を変える能力に欠けています。
意思決定に自信を持てない
強いリーダーシップは、チームをまとめ、一貫したビジョンに向かって進むために不可欠です。意思決定の過程で自信がないと、時には事業に不利益をもたらす方向へ進むことになりかねません。意思決定が遅い、または不確かな人は、ビジネスチャンスを逃すだけでなく、チームの信頼を失い、結果的に事業が失敗に終わることも少なくありません。
起業成功率を高める方法
起業には多くのリスクが伴いますが、それを回避するための方法もあります。ここでは、起業成功率を高めるために有効な3つの方法を紹介します。
副業からスタートする
起業をするときには、最初から本業として始めるのではなく、副業として始めることがおすすめです。副業からのスタートのメリットは以下の通りです。
- 安定した収入源を確保できる
- 市場や顧客のニーズを探ることができる
- 失敗してもリスクが小さい
副業からのスタートは、起業成功率を高めるだけでなく、自分の能力や可能性を広げるチャンスでもあります。
シェアワークオフィスで活動する
シェアワークオフィスとは、複数の企業や個人が共同で利用するオフィススペースのことで、インターネットや電話などの基本的な設備が整っています。シェアワークオフィスで活動することで、コスト削減や人脈の拡大が期待できるでしょう。
シェアワークオフィスは、都市部だけでなく、地方や海外にも多く存在しています。自分のニーズに合ったシェアワークオフィスを探してみましょう。
定期的に事業計画を見直す
起業には様々なリスクが伴います。例えば、資金不足、販売不振、従業員の事故などが挙げられます。これらのリスクに対処するためには、事前に事業計画を作成し、定期的に見直しや修正を行うことが重要です。
事業計画を作成することで、起業の方向性や優先順位を明確にし、必要な資金や人材を確保することができます。また、事業計画は投資家や金融機関に対して自社のビジネスモデルや収益性をアピールするためのツールとしても活用できます。
しかし、事業計画は一度作成したら終わりではありません。市場環境や競合状況、顧客ニーズなどは常に変化しています。そのため、事業計画は定期的に見直しや修正を行い、現実に合わせて柔軟に対応する必要があります。例えば、新しい商品やサービスの開発、価格設定の変更、販路の拡大などの施策を検討することができます。
起業の成功率を知り対策を講じることが大切
この記事では、起業の成功率に関するデータや事例を紹介しました。日本における起業の現状は、決して楽観的とは言えませんが、失敗を回避することは不可能ではありません。
また起業は一朝一夕に成功するものではありません。事業計画の見直しやリスク管理を常に行いながら、長期的な視点で取り組むことが大切です。この記事を参考に、自分ならではの価値を提供できるサービスや商品を開発していきましょう。