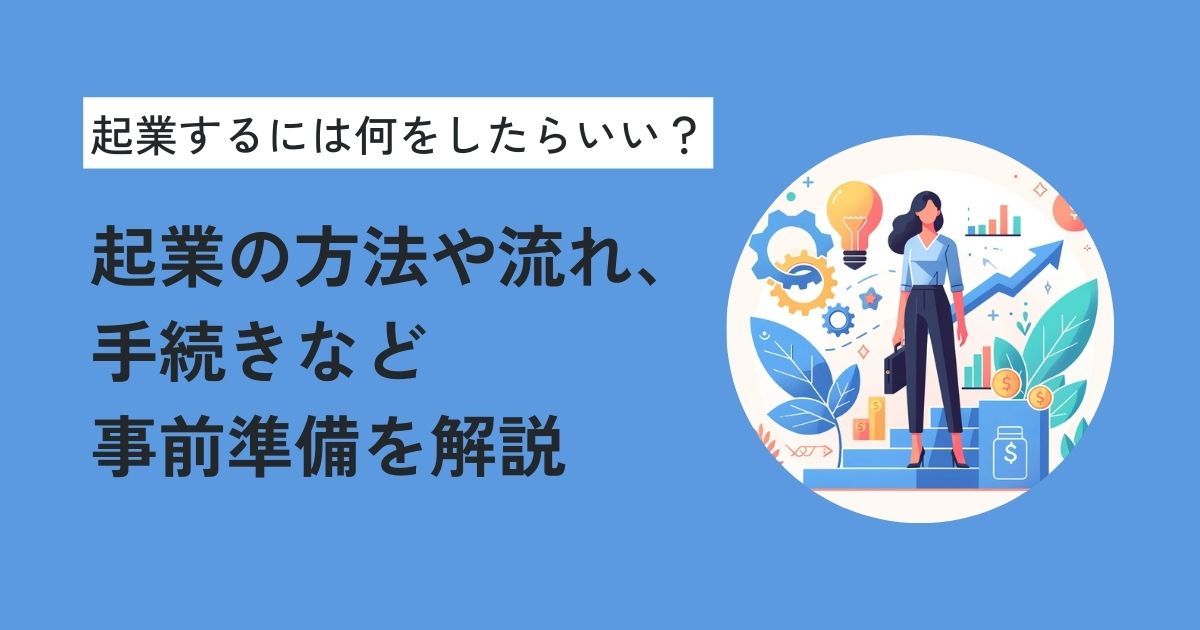起業するには何をしたらいいのか、という疑問を持つ方は多いでしょう。起業には様々なメリットがありますが、同時にリスクや責任も大きくなります。そのため、起業する前にはしっかりと計画を立てることが重要です。
この記事では、起業するまでの手順を7ステップで紹介します。これらのステップを踏むことで、起業の目的やアイデア、形態、資金調達、法人登記などの基本的な知識を身につけることができます。また起業前・起業後に必要なものや、起業の失敗を回避する方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
起業するまでの手順7ステップ
起業とは、自分のアイデアやスキルを活かして、新しい事業を始めることです。ここでは、起業するまでの手順を7ステップで解説します。
1. 起業の目的を明確化する
まず、起業する目的を明確にしましょう。起業する目的とは、自分が何をしたいのか、どんな価値を提供したいのか、どんなビジョンを持っているのかなどです。起業の目的を明確にすることで、自分の強みや弱みを把握できたり、自分に合った事業内容や形態を選べたりします。
また、起業の目的は、自分だけでなく、将来の顧客やパートナー、投資家などにも伝えることができます。これにより、信頼や共感を得られたり、協力や支援を受けられたりします。
2. アイデアの検討と市場調査を行う
次に、起業アイデアを検討しましょう。起業アイデアとは、自分が提供する商品やサービスの内容です。自分の興味や経験に基づいて考えることもできますが、それだけでは不十分です。市場のニーズや競合状況も考慮しながらアイデアを検討し、市場調査を経て事業の形にしましょう。
起業アイデアの見つけ方
起業アイデアを見つけるには、まず自分の周りにある問題やニーズに気づくことが大切です。例えば、以下のような方法で起業アイデアを見つけることができます。
- 自分や身近な人が抱える不満や困りごとをリストアップする
- 自分が得意なことや好きなことをリストアップする
- 既存の商品やサービスに改善点や付加価値を考える
- 海外や他業界の事例やトレンドを参考にする
- インターネットや書籍などで情報収集する
これらの方法で得られたアイデアは、まだ具体的ではないかもしれませんが、市場調査を通してブラッシュアップしていくことができます。
起業したいけどアイデアがない場合の対処法
アイデアがないからといって、起業をあきらめる必要はありません。アイデアは、起業の一部にすぎず、実行力や継続力など、他にも重要な要素があるからです。
どうしても起業したいけどアイデアが思い浮かばない場合は、以下のような対処法があります。
- 他人の成功事例や失敗事例を学ぶ
- 起業家や専門家に相談する
- 起業支援プログラムやコンテストに参加する
- アイデアソンやブレインストーミングなどのクリエイティブな手法を使う
- 自分の考えを書き出したり、発表したりする
これらの対処法は、自分の視野を広げたり、インスピレーションを得たりするのに役立ちます。また、アイデアは、常に変化や改良が必要です。市場や顧客のニーズに合わせて、柔軟に対応していくことが大切です。
関連記事:起業アイデアの見つけ方と思いつかないときの解決策|起業家の成功例も紹介
関連記事:起業したいけどアイデアがない人向けの考え方5選|リスクの低い起業アイデアも
市場調査の方法
市場調査とは、自分の提供する商品やサービスが市場で受け入れられるかどうかを調べることです。市場調査を行うことで、市場の規模や成長性、競合他社の強み・弱みなどを把握でき、それを踏まえて自分の商品・サービスの価格や販売戦略を決められます。
市場調査には、主に以下の二種類の方法があります。
| デスクリサーチ | インターネットや書籍などから既存の情報を収集する方法 |
| フィールドリサーチ | 実際に顧客や競合他社にインタビューやアンケートなどを行う方法 |
デスクリサーチは、比較的簡単かつ安価に行えますが、情報が古くなっていたり、自分に必要な情報が見つからなかったりする可能性があります。フィールドリサーチは、より新鮮で正確な情報が得られますが、時間や費用がかかったり、実施するスキルが必要だったりします。両方の方法を組み合わせ、より効果的な市場調査を実施しましょう。
3. 起業する形態を選定する
次に、起業する形態を選定しましょう。起業する形態とは、自分が事業主として登録する際の法的な形態です。主に以下の三種類があります。
- 個人事業主として起業する
- 法人として起業する
- フランチャイズ制度を利用して起業する
関連記事:起業の種類とは|資金調達方法や起業アイデアの種類も解説
個人事業主として起業する
個人事業主として起業する方法は、最も簡単な起業の形態です。個人事業主とは、自分の名前で事業を行う人のことで、法人格はありません。個人事業主として起業するメリット・デメリットは、以下のようなものがあります。
| メリット | ・開業届けや許可などの手続きが少ない ・会社設立費用や税金が安い ・経理や決算などの手間が少ない ・自分の意思で事業内容や規模を変更できる |
| デメリット | ・自己責任で事業を行うため、借金や損害賠償などのリスクが高い ・法人格がないため、信用力や社会的地位が低い ・税制上の優遇措置や補助金・助成金の利用が制限される ・社会保険や年金などの福利厚生が自己負担になる |
個人事業主として起業する場合、開業届けを市区町村役場に提出する必要があります。また、事業内容によっては、税務署や都道府県庁などに許可や届出を行う必要がある場合もあります。具体的には、以下のような事業に該当する場合です。
- 飲食店や旅館などの営業許可
- 建設業や運送業などの許可登録
- 医師や弁護士などの資格登録
- 消費税の課税事業者登録
関連記事:個人事業主として起業するには|起業前のやることリストと確定申告について
法人として起業する
法人として起業する場合、自分とは別に法人格を持つ組織として事業を行います。法人として起業するメリット・デメリットは、以下のようなものがあります。
| メリット | ・自分と法人を分けることで、借金や損害賠償などのリスクを低減できる ・法人格を持つことで、信用力や社会的地位が高まる ・税制上の優遇措置や補助金・助成金の利用が容易になる ・社会保険や年金などの福利厚生を法人が負担できる |
| デメリット | ・会社設立費用や税金が高い ・経理や決算などの手間が多い ・自分の意思で事業内容や規模を変更することが難しい ・株主や役員との関係性を管理する必要がある |
法人として起業する場合、会社設立の手続きを行う必要があります。会社設立の手続きは、以下のような流れになります。
- 会社の種類(株式会社や合同会社など)を決める
- 会社の名称や目的、資本金、役員などの定款を作成する
- 定款認証を公証人役場で行う
- 資本金を預金する
- 法人登記を法務局で行う
- 印鑑登録や開業届けなどの届出を行う
関連記事:会社設立の流れ5ステップ|必要な手続きや費用・メリットを詳しく解説
フランチャイズ制度を利用して起業する
フランチャイズ制度とは、既に成功している企業(本部)が、自社のブランドやノウハウを提供する代わりに、一定の条件を満たした個人や法人(加盟店)に加盟料やロイヤリティなどを支払わせる仕組みです。フランチャイズ制度を利用して起業するメリット・デメリットは、以下のようなものがあります。
| メリット | ・本部からブランドやノウハウ、商品やサービス、広告や販促などの支援を受けられる ・開業時のリスクや費用が低減できる ・独立しながらも仲間や先輩との交流ができる |
| デメリット | ・本部からの規約や指導に従わなければならない ・加盟料やロイヤリティなどの費用が発生する ・本部とのトラブルや競合店との競争が起こる可能性がある |
フランチャイズ制度を利用して起業する場合、本部と加盟契約を結ぶ必要があります。加盟契約には、以下のような内容が含まれます。
- 契約期間や更新条件
- 加盟料やロイヤリティなどの費用
- 本部から提供される支援内容と義務
- 加盟店から求められる条件と義務
- 契約解除や解約時の処理
4. 事業計画書を作成する
起業するには、事業計画書を作成することが必要です。事業計画書とは、自分の起業の目的やアイデア、市場分析、販売戦略、資金計画などをまとめた文書です。事業計画書は、自分のビジョンを明確にするだけでなく、資金調達やパートナー探しにも役立ちます。
事業計画書の作成には、以下のポイントに注意しましょう。
- 読み手にわかりやすく伝えるために、文章は簡潔に、数字は具体的に記述する
- 自分の強みや競争優位性をアピールするために、差別化要因や独自性を明確にする
- 現実的かつ合理的な計画であることを示すために、市場調査や財務分析の根拠を示す
- 読み手の信頼を得るために、自分の経歴や実績、チームメンバーの紹介を入れる
事業計画書のフォーマットは決まっていませんが、一般的には以下のような項目を含めるとよいでしょう。
- 表紙(タイトル、氏名、連絡先など)
- 目次
- 概要(事業内容、目的、市場規模、収益予測など)
- 事業内容(アイデアの概要、商品・サービスの特徴、価格設定など)
- 市場分析(ターゲット市場、顧客ニーズ、競合分析など)
- 販売戦略(販路開拓、プロモーション、ブランディングなど)
- 組織・人材(組織図、役割分担、人材確保・育成など)
- 資金計画(資金調達方法、資金使途、収支予測など)
- リスク分析(事業に関するリスクと対策)
- 付録(参考資料や補足情報など)
5. 資金調達を行う
起業するには、資金が必要です。資金調達には様々な方法がありますが、主な方法は以下の4つです。
- 自己資金を資本とする
- 出資を受ける
- 融資を受ける
- 補助金・助成金を活用する
関連記事:起業に使える資金調達方法まとめ|それぞれのメリットや資金調達の注意点も
関連記事:起業にかかる費用はどのくらい?費用目安と資金調達方法を解説
自己資金を資本とする
自己資金とは、自分自身が持っているお金や貯蓄のことです。自己資金を資本として起業するメリット・デメリットは、以下のようなものがあります。
| メリット | ・返済義務や利息が発生しないため、財務的な負担が少ない ・他人から干渉されずに自由に経営できる ・自己資金が多いほど、他の資金調達方法においても信用度が高まる |
| デメリット | ・自己資金が少ないと、起業に必要な資金が足りない可能性がある ・自己資金を全て使ってしまうと、万が一のリスクに備える余裕がなくなる ・自己資金だけでは、事業の拡大や成長に限界がある |
出資を受ける
出資とは、特定の団体や個人から資金を提供を受けて事業を始めることです。出資を受けるメリット・デメリットは、以下のようなものがあります。
| メリット | ・大きな資金を調達できる可能性がある ・出資者からのアドバイスやネットワークを活用できる ・出資者との信頼関係が築ければ、追加の出資や協力を得やすい |
| デメリット | ・出資者に対して利益や権利を分配しなければならない ・出資者からの要求や干渉に応じなければならない場合がある ・出資者との意見や方針が合わないと、トラブルになる可能性がある |
融資を受ける
融資とは、銀行や金融機関からお金を借りることです。融資を受けるメリットは、以下のようなものがあります。
| メリット | ・返済期間や利率などの条件を交渉できる場合がある ・融資額に応じて税制上の優遇措置を受けられる場合がある ・融資先からの信用力や信頼度が高まる |
| デメリット | ・返済義務や利息が発生するため、財務的な負担が大きい ・担保や保証人を求められる場合がある ・審査基準や条件が厳しい場合がある |
補助金・助成金を活用する
起業では、補助金や助成金といった公的な支援制度も利用できます。補助金とは、国や地方自治体などが事業者に対して無償で支給する金銭のことで、助成金とは、社会保険料や雇用保険料などの負担を軽減するために支給される金銭のことです。
補助金・助成金には、以下のようなメリット・デメリットがあります。
| メリット | ・返済不要のお金をもらえる ・起業の信頼度が向上する ・事業計画をブラッシュアップできる |
| デメリット | ・条件に合わなければ申請できない ・手続きが煩雑 ・前払いではない |
補助金や助成金を受けるには、それぞれの制度の対象となる条件を満たし、申請書や事業計画書などの必要書類を提出する必要があります。また、補助金や助成金は予算に限りがあるため、応募者が多い場合は審査や抽選が行われます。補助金や助成金の種類や内容は多岐にわたるので、自分の事業に合ったものを探してみましょう。
関連記事:女性起業家におすすめの助成金・補助金まとめ|申請時の注意点も解説
6. 法人登記をする(法人として起業する場合)
法人として起業する場合は、法人登記を行う必要があります。法人登記とは、会社の設立や変更などの事項を法務局に届け出て公示することです。法人登記をすることで、会社が法的に認められるとともに、会社名や代表者名などの情報が公開されます。
ここでは、株式会社を設立する際に必要な書類や法定費用について解説します。
法人登記に必要な書類
法人登記に必要な書類のうち、代表的なものは以下の通りです。
- 定款(印紙税15万円分を貼付)
- 登記申請書(印紙税4千円分を貼付)
- 登記事項証明書(代表者や役員の住所・氏名・印鑑などを証明する書類)
- 印鑑証明書(代表者や役員の印鑑を登録した証明書)
- 身分証明書(代表者や役員の運転免許証やパスポートなど)
- 委任状(代理人が申請する場合に必要)
これらの書類は原則として自分で作成することができますが、内容に不備があると登記が受理されない場合があります。また、定款は会社の基本的なルールを定める重要な文書なので、専門家に依頼することも検討しましょう。
法人登記にかかる費用
法人登記にかかる費用は以下の通りです。
- 印紙税:19万4千円(定款15万円+登記申請書4千円)
- 登録免許税:15万円(資本金1000万円以下の場合。資本金が多いほど増額)
- 登記手数料:4千円
- 専門家への報酬:5万円~20万円程度(任意)
合計すると、最低でも約24万円はかかることになります。また、登録免許税は法人設立後に納付する必要がありますが、納付期限は法人設立の翌月末日までなので注意しましょう。
7. 事業を開始する
法人登記が完了したら、いよいよ事業を開始することができます。事業を開始するにあたっては、以下の点に注意しましょう。
- 開業届を提出する(個人事業主として起業する場合も同様)
- 税務署や社会保険事務所などに必要な届出を行う
- ホームページや名刺などの宣伝ツールを作成する
- 仕事場所や備品などの準備を整える
- 営業活動や顧客対応などの業務を行う
起業はゴールではなくスタートです。事業を開始したら、常に市場や顧客のニーズに応えられるように改善や挑戦を続けていきましょう。
起業前・起業後に必要なもの
ここまで、起業するまでのステップを解説しました。本章では、起業前・起業後に必要なものとして以下の5つを紹介します。
- ホームページ
- 名刺
- 仕事場所
- 会社案内資料
- 営業資料
ホームページ
ホームページは、起業家の顔とも言えるものであり、インターネットで検索されたときに自分の事業内容や強みをアピールできる場所です。お客様からの問い合わせや資料請求などを受け付けることもできるため、必ず用意しましょう。
ホームページの作成は、自作・外注と2つの方法があります。
| 自分で作成する方法 | ホームページ作成ツールやテンプレートを利用して、自分でホームページを作成する方法。費用は安く済むものの、時間やスキルが必要となる |
| 外注する方法 | ホームページ制作会社やフリーランスに依頼して、ホームページを作成する方法。費用は高くなるものの、プロに任せることができる |
ホームページを作成する際には、ターゲット層に合わせたデザインやコンテンツを用意したり、検索エンジンで上位に表示されるためにSEOを実施したりといった工夫が必要です。また更新頻度やメンテナンス費用などについても考慮しましょう。
名刺
名刺は、起業家として最初に交換するアイテムです。自分の事業内容や連絡先を伝えるだけでなく、印象や信頼感を与える役割もあります。
名刺の作成は、デザインソフトを使えば自分で作成することも可能です。外注する予算がない場合は、自作も検討してみましょう。
仕事場所
仕事場所は、起業家の作業環境やイメージに影響するものです。仕事場所の候補としては、以下の4つが挙げられます。
- 自宅
- レンタルオフィス
- コワーキングスペース
- 自分でオフィスを構える
仕事場所を決める際には予算だけでなく、アクセスや立地条件、契約期間や条件を確認するようにしましょう。
会社案内資料
会社案内資料は、事業内容や強みを伝えるためのものです。会社案内資料を作成するには、自作もしくは外注の2つの方法があります。
| 自分で作成する方法 | パワーポイントやワードなどを利用して、自分で会社案内資料を作成する方法。費用は安く済むものの、時間やスキルが必要 |
| 外注する方法 | 制作会社やデザイナーに依頼して会社案内資料を作成する方法。費用は高くなるものの、プロのデザインや文章を得ることができる |
会社案内資料を作成する際には、以下の点に注意しましょう。
- ターゲット層に合わせた内容やトーンにする
- 事業内容や強みを具体的に示す
- 見栄えや読みやすさに配慮する
営業資料
起業するときには、自分の事業や商品・サービスをお客様に紹介するための営業資料が必要です。営業資料を作成する際には、以下のポイントに注意しましょう。
- ターゲットとなるお客様の特徴や状況を把握する
- 自分の事業や商品・サービスの強みや差別化点を明確にする
- お客様のメリットや価値を具体的に示す
- 信頼性や安心感を高めるための証拠やデータを用いる
- 見やすくわかりやすいデザインやレイアウトにする
- アクションを促すための呼びかけや連絡先を入れる
営業資料は会社案内資料同様に、パワーポイントなどのツールを使って自作することができます。
起業の失敗を回避するには
起業は夢を実現するための挑戦ですが、同時にリスクも伴います。中小企業白書(2017年)によると、起業した企業の5年後生存率は81.7%と言われています。では、起業の失敗を回避するにはどうすればいいのでしょうか?ここでは、起業の失敗を回避するための3つのポイントを紹介します。
- 資金管理を徹底する
- スモールスタートから始める
- 常に新しい情報をインプットする
参考:中小企業白書 第2部 中小企業のライフサイクル|中小企業庁
資金管理を徹底する
起業の失敗の最大の原因は、資金不足です。資金不足に陥ると事業活動が滞り、顧客や取引先から信用を失い、最悪の場合は倒産してしまいます。そうならないためには、資金管理を徹底する必要があります。資金管理とは、収入と支出のバランスを把握し、必要な資金を確保することです。具体的には、以下のようなことを行います。
- 事業計画書に基づいて予算を立てる
- 収入と支出を記録し、定期的に精算する
- キャッシュフローを予測し、資金繰り表を作成する
- 資金不足に備えて貯蓄や借入などの手段を検討する
- 無駄な支出やリスクの高い投資を避ける
資金管理は起業家の基本的なスキルです。常に資金状況を把握し、適切な判断と対策を行いましょう。
スモールスタートから始める
起業には大きな夢やビジョンが必要ですが、それだけでは成功できません。実際に市場で受け入れられるかどうかは、試してみなければわかりません。そこで、スモールスタートという方法がおすすめです。
スモールスタートとは、小さく始めて、少しずつ成長させていくことです。具体的には、以下のようなことを行います。
- 最小限のコストで最小限の製品やサービスを開発する(ミニマム・バイアブル・プロダクト)
- 実際に顧客に提供してフィードバックを得る(検証)
- フィードバックに基づいて製品やサービスを改善する(改善)
- このサイクルを繰り返して市場ニーズに合わせて進化させる(継続)
スモールスタートは、市場の反応を早く知ることができるだけでなく、失敗したときのダメージも小さく抑えることができます。また、顧客との関係も強化できます。大きく飛び込む前に、まずは小さく始めてみましょう。
常に新しい情報をインプットする
起業の失敗を回避するためには、競合他社の動向や顧客のニーズ、技術の進歩や法律の変更など、常に新しい情報をインプットするようにしましょう。情報をインプットすることで、以下のようなメリットがあります。
- 自社の強みや弱みを把握することができる
- 市場の変化に対応することができる
- 新しいアイデアやビジネスモデルを生み出すことができる
- 自分の知識やスキルを向上させることができる
新しい情報をインプットするためには、インターネットや書籍だけでなく、セミナーや勉強会、業界の専門家や先輩起業家などのつながりなども活用しましょう。
起業で成功するには綿密な事前準備が不可欠
この記事では、起業するには何をしたらいいか、方法や流れ、手続きなど事前準備を解説しました。
起業にはリスクがありますが、それ以上に大きな魅力もあります。自分の夢やビジョンを実現するために、ぜひ今回の記事を参考に挑戦してみてください。