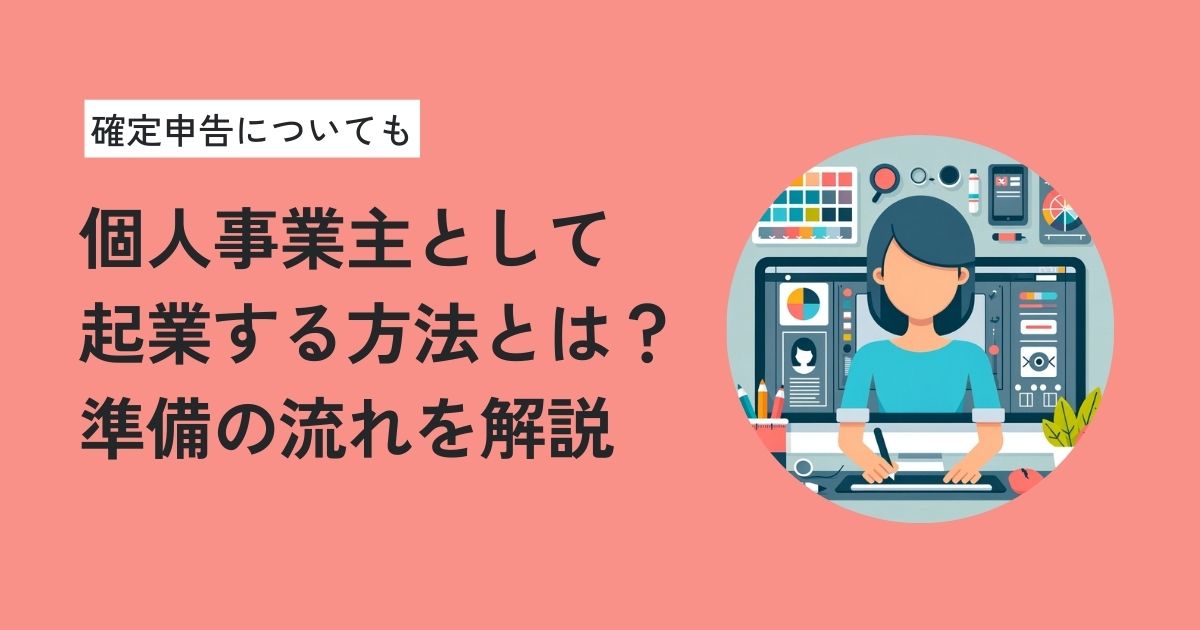個人事業主になるには、法人とは違った手続きや準備が必要です。また、個人事業主は自分で確定申告を行わなければなりません。この記事では、個人事業主として起業するにあたって知っておくべきことややるべきことをまとめてご紹介します。
関連記事:起業するには何をしたらいい?方法や流れ、手続きなど事前準備を解説
個人事業主とは?法人との違い
個人事業主とは、個人で事業を行う人のことです。法人とは、会社や団体などの組織で事業を行うことです。個人事業主と法人には、税金や責任などの面で大きな違いがあります。
個人事業主の場合、自分の収入がそのまま事業所得となります。そのため、所得税や住民税を自分で計算して納める必要があります。また、自分の財産は事業資産と区別されず、事業に関する債務や損害賠償などのリスクに対しても自己責任となります。
法人の場合、組織が独立した主体として認められます。そのため、組織の収入は法人税として納められ、組織の財産は個人の財産と区別されます。また、組織に関する債務や損害賠償などのリスクに対しても、原則として組織が責任を負います。
個人事業主と法人には、それぞれメリットとデメリットがあります。個人事業主は、手続きが簡単で自由度が高い反面、税金やリスクが大きくなります。法人は、手続きが複雑で制約が多い反面、税金やリスクを軽減できます。自分の事業内容や目標に合わせて、最適な形態を選択することが重要です。
関連記事:起業の種類とは|資金調達方法や起業アイデアの種類も解説
関連記事:会社設立の流れ5ステップ|必要な手続きや費用・メリットを詳しく解説
個人事業主になるには?準備とやることリスト
ここでは、個人事業主になるための準備を紹介します。
1. 事業計画を立てる
個人事業主として起業するには、まず事業計画を立てることが重要です。事業計画とは、自分の事業の目的や目標、市場や競合の分析、販売戦略や財務計画などをまとめた文書です。事業計画を作成することで、自分の事業の方向性や強み、課題やリスクを明確にし、効果的な経営を行うことができます。
事業計画を作成する際には、以下のポイントに注意しましょう。
- 事業計画は自分だけでなく、他の人にもわかりやすく書く
- 事業計画は定期的に見直し、必要に応じて修正する
- 事業計画は具体的かつ現実的に書く
事業計画を作成する方法はいくつかありますが、一般的なものとしては「ビジネスモデルキャンバス」というツールがあります。ビジネスモデルキャンバスとは、9つの要素(価値提案、顧客セグメント、チャネル、顧客関係、収益源、キーリソース、キーアクティビティ、キーパートナー、コスト構造)を1枚の紙に書き出すことで、自分の事業の全体像を把握することができるツールです。ビジネスモデルキャンバスを使うことで、自分の事業の強みや弱み、改善点や新たな可能性を発見することができます。
2. 社会保険の切り替え
個人事業主になると、会社員時代に加入していた社会保険から国民保険に切り替える必要があります。社会保険と国民保険の違いや、切り替えの方法について説明します。
国民健康保険への加入
個人事業主は、国民健康保険に加入することが義務付けられています。国民健康保険は、病気やけがなどで医療を受けた際に、一定の割合で費用を補助する制度です。国民健康保険の加入方法は、以下の通りです。
- 開業届を提出した後、住所地の市区町村役場に国民健康保険の加入届を提出する
- 市区町村役場から国民健康保険証が交付される
- 国民健康保険料の支払い方法を決める。支払い方法は、口座振替や納付書での振込などがある
国民健康保険料は、前年度の所得や家族構成などによって決まります。個人事業主は、所得が変動する可能性が高いため、毎年確定申告を行って所得を正確に申告することが重要です。確定申告を行わないと、過大な保険料を請求されることがあります。
国民年金への加入
個人事業主は、国民年金に加入することが義務付けられています。国民年金は、老後や障害などで働けなくなった場合に、一定の基礎的な生活費を支給する制度です。国民年金の加入方法は、以下の通りです。
- 開業届を提出した後、住所地の市区町村役場に国民年金第一号被保険者としての加入届を提出する。
- 市区町村役場から国民年金手帳が交付される。
- 国民年金料の支払い方法を決める。支払い方法は、口座振替や納付書での振込などがある。
国民年金料は、全国一律で月額16,770円(令和3年度)です。ただし、個人事業主は、所得に応じて免除や減額の申請ができます。免除や減額の申請は、毎年確定申告と同時に行うことができます。確定申告を行わないと、免除や減額の対象にならないことがあります。
3. 資金調達と銀行口座の準備
個人事業主として起業するには、開業資金の計画と事業用口座の用意が必要です。。ここでは、開業資金の計画と事業用口座の用意について説明します。
開業資金の計画
個人事業主として起業するには、開業資金の計画が重要です。開業資金とは、事業を始めるために必要な資金のことで、以下のようなものが含まれます。
- 事業用の備品や設備の購入費用
- 事務所や店舗の家賃や光熱費などの固定費用
- 広告宣伝費や営業交通費などの変動費用
- 生活費や税金などの個人的な支出
開業資金の計画を立てる際には、事業が軌道に乗るまでに必要な期間分(一般的には最低でも半年分)を見積もることが望ましいといえます。また開業資金は、自己資金と借入金のバランスを考えることが大切です。収支予測表やキャッシュフロー表などの財務計画書を作成することで、より具体的に把握することができます。
事業用口座とクレジットカードの用意
個人事業主として起業する場合、事業用の口座とクレジットカードを用意することがおすすめです。事業用の口座とクレジットカードを使うことで、以下のメリットがあります。
- 事業収入と個人収入を分けて管理できる
- 経費の計算や帳簿の記録がしやすくなる
- クレジットカードのポイントやキャッシュバックなどの特典を利用できる
- 資金繰りに余裕ができる
事業用の口座とクレジットカードは、開業前に準備しておくとスムーズに事業を始められます。しかし、どの銀行やカード会社を選ぶかは、個人事業主の事業内容や規模によって異なります。以下のポイントを参考にして、自分に合ったものを選びましょう。
- 手数料や利率などの条件を比較する
- ネットバンキングやATMなどの利便性を考慮する
- 信用力や審査基準などの要件を確認する
- サポートや相談窓口などのサービスを評価する
4. 開業届を提出する
個人事業主として起業するには、開業届を税務署に提出する必要があります。開業届は、事業の開始日から2ヶ月以内に提出するのが原則です。開業届を提出することで、個人事業主としての税務上の手続きが始まります。
屋号の意義とメリット
開業届を提出する際には、屋号を記入する欄があります。屋号とは、個人事業主が事業を行う際に使用する名称のことで、法律上の義務ではありませんが、任意で登録することができます。屋号を登録することには、以下のようなメリットがあります。
- 事業のイメージやブランドを表現できる
- 顧客や取引先からの信頼感や親近感を得られる
- 同じ分野の他の個人事業主と差別化できる
- 自分の名前以外の名前で事業を行いたい場合に便利
屋号を登録する場合には、既に登録されている屋号や商標と重複しないように注意しましょう。また、公序良俗に反するような屋号や、誤解を招くような屋号は避けるべきです。
青色申告承認申請書の提出
開業届と同時に、青色申告承認申請書も提出することをおすすめします。青色申告とは、個人事業主が確定申告を行う際に選択できる申告方式の一つで、帳簿を正しく記録していることを条件に、税務上の優遇措置を受けられる制度です。青色申告を選択することには、以下のようなメリットがあります。
- 所得控除額が高くなる
- 損失があった場合に繰越控除ができる
- 青色専用配偶者控除が受けられる
- 確定申告の期限が延長される
- 電子帳簿保存制度や電子申告・納税制度が利用できる
青色申告承認申請書は、開業届と同じ税務署に提出します。承認されると、承認証明書が発行されます。青色申告承認申請書は、事業開始日から1年以内に提出する必要があります。
5. 許認可の申請を行う
個人事業主として起業する場合、事業の内容によっては許認可が必要になることがあります。許認可とは、国や地方自治体などの公的機関から事業を行うための許可や認可を受けることをいいます。許認可が必要な事業は、飲食店や美容院、旅館などの営業許可や、医師や弁護士などの資格証明書などがあります。
許認可が必要な事業を行う場合は、開業前に必ず申請手続きを済ませておく必要があります。申請手続きには、書類の作成や提出、審査や検査などが含まれます。申請手続きにかかる時間や費用は、事業の内容や規模によって異なりますが、一般的には数週間から数ヶ月程度かかることが多いです。また、申請手続きには専門的な知識や技術が必要な場合もありますので、必要に応じて専門家に相談することも検討しましょう。
個人事業主が理解しておくべき確定申告について
個人事業主として起業すると、毎年確定申告を行う必要があります。確定申告とは、自分の収入や経費を税務署に報告し、所得税や消費税などの納税額を計算することです。確定申告を正しく行うためには、帳簿の記録と確定申告方式の選択が重要です。
帳簿の記録
帳簿とは、事業に関する収入や支出を記録したものです。帳簿には、日々の売上や仕入れ、経費などを記入する「日記帳」と、月ごとに収支をまとめる「総勘定元帳」があります。帳簿は、確定申告の根拠となる資料であり、税務調査の際にも必要です。そのため、帳簿は正確かつ詳細につけることが求められます。
帳簿の記録方法には、手書きやエクセルなどで自分で作成する方法と、会計ソフトやクラウドサービスなどを利用する方法があります。現在では、会計ソフトやクラウドサービスを利用する方法が一般的でしょう。会計ソフトやクラウドサービスを利用する場合は、費用や機能性などを比較検討し、自分の事業に合ったものを選ぶ必要があります。
確定申告方式の選択
確定申告方式には、「白色申告」と「青色申告」の二種類があります。白色申告とは、帳簿をつける必要がなく、収入から経費を差し引いた金額を所得として申告する方法です。青色申告とは、帳簿をつける必要があり、帳簿に基づいて所得を計算し申告する方法です。
白色申告と青色申告では、所得税や消費税の計算方法や控除額などが異なります。一般的には、青色申告の方が税金が安くなるメリットがあります。しかし、青色申告では帳簿の作成や保存などの手間がかかります。また、青色申告には承認制度があり、開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出する必要があります。
確定申告方式は、自分の事業規模や経理能力などに応じて選ぶことができます。確定申告方式の変更も可能ですが、変更する場合は期限内に届出書を提出する必要があります。
個人事業主の準備は慎重に進めよう
この記事では、個人事業主として起業するにはどのような準備や手続きが必要なのか、また確定申告についての基本的な知識を紹介しました。個人事業主として起業することは、自分の夢や目標を実現するためのチャレンジです。しかし、そのためには様々な知識やスキルが求められます。この記事が、個人事業主として起業する前に知っておくべきことや確定申告についての参考になれば幸いです。